 |
| 活動状況 |
 |
相互評価(ピアレビュー) |
 |
|
 |
2004年 2月16日
|
第37回相互評価(ピアレビュー)に参加頂いた
第三者オブザーバーのご意見・ご感想について
|
2003年12月9日から12日の間、東京電力(株)福島第二原子力発電所(福島県双葉郡富岡町及び楢葉町)に対して実施した第37回ピアレビューにおいて、NSネットの会員外から科学技術ジャーナリストである尾崎正直氏に2日間(9日及び10日)にわたりオブザーバー参加頂きました。その際のご意見・ご感想が以下の通り取りまとめられましたので、ご紹介致します。 |
1.はじめに |
私は第一回のピアレビューが三菱原子燃料(株)で行われる数日前に取材に行ったが、社内では準備で大変な苦労をしていたという印象がある。JCOの事故が起こった直後だったので、臨界管理がいかに入念にかつ綿密に行われているかということを見せてくれた。その当時の感じとしては、電力には「あんな事故はJCO特有のことで、電力会社には絶対に起こりえない」というふうなことを公言する人もおり、私達もそう思っていた。
ピアレビューのワンクール36社が終わって、今回が37社目、今日でNSネット設立4周年だそうだが、これがまさかこの東京電力(株)のような電力業界のピラミッドの頂点に立つ企業に対して行われるとは、あの当時は思いもしなかった。そういう意味では、ピアレビューに関連企業を全部含めた意味もまたあったのではないかと思っている。 |
2.ピアレビューについて |
今回のようなピアレビューは、いわゆるPDCAといったものに活かして頂ければ、大変成果があるのではないかと思う。
ただ、一見して、ピアレビューのために準備される書類は膨大なものだったと思う。これを作るためにどれくらいの期間を要したか? 費用あるいは労力に見合うだけの効果があるのかな?というような疑問を私は正直言って持った。もともとがJCOとは違うのだという認識でスタートしたピアレビューなので、皆さん方みたいな大企業の、しかも入念に整理された書面から見る限り、欠けるようなものは出てこないと思う。数人のレビューアが質問や書類審査に数時間かけるだけで、欠点が洗い出せるものではない。ひとつ意味があるとすれば、この機会を利用して、皆さん方が自分達の日頃の仕事を整理し、あるいは反省するきっかけになれば、それなりの効果はあると思う。よく言われるが、こうした組織は一度創ってしまうと、なかなか崩すことは難しい。がしかし、一巡したのであるから、皆さん方の意見を入れてピアレビューのやり方などを再検討する時期にきているのではなかろうか。 |
| 3.東電問題について |
今度の東電の問題で、「最大のものは地域の信頼を失ったということである。いかにして信頼を回復するかに全力をあげる以外にない。基本的には安全を最優先として、その取り組みと実績を地域の方々にお見せして行くしかない」とピアレビューの冒頭に所長も話されたが、その通りだと思う。
よく言われるが、安全は技術の問題であり、努力することによりなんとか解決できるが、安心は心の問題であって、どこまでいったら安心か際限が無い。技術だけでは解決できない、社会学的にも難しい問題に、皆さん方は取り組もうとしているわけで、時間がかかるだろうと思う。
東電の問題について外国の報道を追跡していたのだが、ニューヨークタイムズは、東電の南社長さん以下4人の前元首脳陣が辞職を表明した段階で、データ改ざんなど事実を淡々と報じた。だが、見出しには「事故」ではなく「核スキャンダル」という言葉が使われていた。東電のスキャンダル。要するに、大企業の倫理観といったものがむしろ問われたわけである。「俺は知らなかった」では通用しない。これが一般世間の常識である。あのころ、大企業の倫理観が問われる事例がいっぱい出てきて、たまたまこの東電の問題もその一連の枠組みの中で報道され、大きくなったという側面があったわけである。
東電問題で内部告発をしたGEIIの元社員の日系二世がこの10月に来日した。テレビ局のTBSが呼んだらしいのだが、福島へ来て佐藤知事さんと会ったようであるが、彼は「東電にはたいへん迷惑をかけた。あんな大きなことになるとは思わなかった」と言ったそうだ。今朝も私のホテルにGEIIから派遣された大勢のアメリカ人が泊まっていたが、クリスマス休暇もなしに働いて、これが終わったら台湾へ行くと言っていた。一人ひとり話してみると、非常に気さくで、いわゆるヤンキー気質そのままの連中である。そういう中で、どうしてあの日系人だけが内部告発をしたのか、そういったところにも大変興味がある。
歴史を考えてみると、この福島第二原子力発電所で印象に残っているのは、何といっても昭和64年元旦の3号機の再循環ポンプの振動、あるいはポンプの羽根車の破壊である。あの時、NHKのニュースで佐藤知事がものすごい剣幕で怒っているのが画面に大写しになったのをいまだに憶えている。やはりこれがこの発電所で、これまでの一番大きな事故だったのではないかと思う。その負の遺産というものがどう活かされているのか? と言ってもずいぶん古い話で、皆さん方にはもう風化してしまっているのかもしれないが。やはり負の遺産というものはモニュメントとして飾ることによって絶えず身を引き締めるというか、思いを新たにする効果はあるのではないかと思う。
このトラブルでは人命の被害なかったが、事故を大きくした原因について、こんな話しを耳にした記憶がある。正月に皆他の火力等が休んでいる時だけに、原子力を止めると他の火力の人達まで正月休み返上で出て来なければならない、迷惑をかけるという仲間意識があったというのである。事実かどうかは知らないが、そんな小さな仲間意識が結局大きな被害を生んでしまったということになるのではないか? 事故隠し、データ改ざんといった不祥事にも、同じそういったものが流れていたのではないかと思った。
(注:再循環ポンプの破壊事故は、あと数日で定期検査に入るので、何とかそれまでは運転を続けたいと無理をしたのが原因だったという説明を受けた) |
| 4.国や自治体の対応について |
地域差と言うのであろうか、いわゆる原子力地帯といったところが日本には福島県と新潟県と福井県とあるが、福島県だけが知事以下、対応が少し違うという印象を与えている。今度の東電の問題で夏場の停電が心配された時に、日経新聞が「福島県知事は電力供給を『人質』にとっている」と書いていたのを記憶している。正直にいって、そうも言いたくなるような気持ちを、皆さん方もお持ちになっていたのではなかったかと思う。
今年10月から新しい原子力発電設備の検査制度がスタートした。ピアレビューでも、実際この新しい検査制度にどう対応しているかということを期待して来たが、まだなかなかそこまではいってないようである。それも当然で、国策民営とか言われるようで、やはり国の都合次第で組織もめまぐるしく変わっている。どうしてそう変わってきたか私も理解できない部分もあるが、おそらく国の政策自体、あるいは電気事業法の改革が頻繁に行われて、それに対応して電力会社も引っ張られてということだろうと私は理解している。電力事業は地域独占が許されている一方で、電気料金や発電所の建設にも国の方針が大きく影響し、電力会社の自由裁量というものが制限されている。そういった制約のもとに、皆さん方がいろいろ苦労されていることもある程度理解できる。
国が安全宣言を出しても、すぐ運転を再開させてもらえないような状況、こういったものが「いったい法治国家としてありうるのか?」とも思う。もっと言えば「福島県知事に何の権限があるんだ」と言いたくなるようなことを思ったこともある。しかし何といってもやはり地域と共存しないことには原子力発電は続けられないという、皆さん方の気持ちはよく分った。考えてみると、皆さん方のほとんどは福島県民でもあるわけですものね。
新聞論調で言えば、地元の「福島民友」は、論説がものすごく厳しい。東電問題が起こってから二ヶ月くらいの間に十数回、原発関連の論説を立て続けに書いたが、その内容は反対派の教科書みたいになっていると聞いた。それだけではない。例えば県の原子力安全対策室が出しているパンフレットは、反対派があれを読みましょうとインターネットで推薦している。そういった雰囲気の中で皆さん方が広報活動をいろいろやろうとするのも、大変辛い立場であるということも十分理解できる。 |
| 5.受益範囲の局所化 |
ここ双葉郡の人達は、止めている原発をすぐ動かしてくれ、そしてまたあと二つくらい増設してくれと言う声もあるとか。その理由を考えてみれば、原子力は地域の利益にかない、原子力による地域の優遇があるからであるが、同じ県内でも少し離れるとあまり利益が無い。逆に被害が及ぶ恐れがある。しかも双葉郡の町村の人口は非常に少ない。こういった及ぶ利益、受益範囲の局所化ということがいろいろな意味で影を投げかけていると思う。
例えば福井県で知事選挙があり、西川さんという、前の知事の後を継ぐ方と、原子力施設はもう結構だと主張する外交官出身の方と競り合になった。西川さんが辛うじて勝ったのだが、福井県は「嶺北」「嶺南」という二つの地域にわけられるが、西川さんは敦賀を中心とする嶺南の票で勝った。実は嶺南地区は人口が少ない。ただ、双葉郡の人口は嶺南よりももっと少ないので、例えば佐藤知事の5選を止めようと思っても、それは無理というものだ。
逆に一度利益を得てしまった例であるが、今、下北半島の青森県東通村に東北電力が原子力発電所をひとつ建設中である。あと東京電力がふたつ建設する計画があるそうである。その三つができるのを当て込み、その村は下北半島を一市にしようという話に絶対乗ってこない。原発の利益を自分達だけで独り占めしようということだ。また、新潟県の刈羽村もそうである。原発で充分利益を得ているから、柏崎とは絶対合併しないといっている。 |
| 6.新検査制度と維持規格 |
次に「維持規格」の問題だが、導入されたばかりで、どのくらい皆さん方に浸透しているか? 私は維持規格ができれば、もう全部安全だと一般の人たちに思わせてはいけないと思う。維持規格といっても、当面は恐らくシュラウドだけの問題であろう。例えば、再循環系統のパイプ類のように、溶接線の長いものについては、すぐに維持規格は作れないのではないかと、専門外だが思ったりする。しかしジャーナリストも含めて一般の人は、「もう維持規格が全部できた。もう安全だ」と思っているのではないかという気もする。そう思わせて否定しないでおけば、万一、関連した事故が起こった場合、ジャーナリズムから大変な反撃を食らうし、一般の人たちの不信感も以前にも増して増幅されるのではないか、と危惧している。
新しい検査制度の今までと違う点は、制度の枠組みの徹底的な透明化、そして、透明な安全行政、規制行政の実施にある。さらには事業者である皆さん方の安全確保活動にも反映されていくといった、安心の基である信頼関係を築き、そしてやがて安心を生むといったことにも結び付けていこうというのが、新しい検査制度の理念だと聞いている。もちろんアメリカが先行した訳だが、アメリカの規制委員会はいわゆる確率論的な安全評価を導入した。
やはりアメリカもいろいろな事故や事象が起こり、こういった規格ができた訳であるが、この確率論的な安全評価に一番大事なことはデータの積み重ねだ。現在日本では行政側も、あるいは皆さん方事業者側もデータの蓄積は不十分だと思う。10月から導入された新しい検査制度も、まだ確率論的な安全評価というのは導入できないと思う。というのは、例えばシュラウドも新しく取り替えてしまっている。朝日新聞が社説で「傷は隠すものではなくて、安全を担保するための糧だ」と書いていた。医者に患者のカルテがちゃんと保存してあるが、あれが無くなると的確な診断ができなくなるのと同様に、原子力関係の傷においても重要なものだと思う。
最近「負の遺産」という言葉がよく使われるようになった。マイナスの部分、これは決して恥ではない。これを新しい財産として、そして将来の安全に活かそうという前向きの考え方だと思う。最近では「失敗学のすすめ」というような本も出ている。従って、こういったものを「悪」と決めつけるのではなく、むしろ将来への飛躍の糧とするといった考え方がだんだん拡がってきた訳である。是非、こういった考え方の上に立ってこれからもやって頂きたい。
いずれにしても、維持基準が導入されたからといって、安全性が保たれるものではない。ただ残念ながら、今回の一連の流れを見ていると、ジャーナリストも世間一般の人も「維持基準が導入される、これでもう安全は保たれる」という感覚の意見と、「これは傷があっても動かすための、まやかしではないか」という反対の意見が渦巻いている。やはりこれまでの日本の原子力発電所は、傷の発見イコール補修取替えといった考えできており、いわゆる予防保全で、シュラウドもその前提に立って、東電は数年前から取り替えてきた。
しかし、傷発見イコール補修取替えでやってきたために、こんどの過ちにつながった面があることも否定できない。国も事業者からトラブルの報告があるとすぐプラントを停止するとか、規制を強化するといった対応で、やってきた。そういったことが嫌だから、報告を怠るといった悪循環が出てきた。従って、今回の問題は事業者側だけに責任があった訳ではなくて、そういった国側の態度もまた責められるべきである。結局、そういった国の姿勢が電力会社を萎縮させたとも言えるのではないかと思う。
今回、東電は軽微な情報までも公表するようになって、インターネットでも配信している。ただこれだけではもったいない。これはデータベース化して蓄積した上で、事故を少なくする具体策とか研究に役立てて欲しい。
前述のように、新しい検査制度は未だに整備途上のものである。その枠組み、限界といったようなものが一般の国民に理解され、その運用状態が透明化されて初めて一般の人たちから安全確保の状況が見えるようになる。それがまた安心につながっていくのではないかと思う。
今回の一連の問題は、BWR特有の部位で起こっている。PWRに無い部分である。PWRを導入している関西電力などは、保全の近代化を進めている。技術の進歩に応じて、あるいは経験の蓄積をベースにして、仕事で決められていた、時間的頻度でやっていたような状態を、状態監視保守といったものに切り替えつつあると聞いている。プラントひとつひとつをばらばらにして、各パーツの損傷度を全部洗い出して、これをデータベース化した。その結果、パーツ毎に傾向管理ができるので、PWRでは二次系のトラブルはほとんど新聞沙汰にならなくなったという。もちろんこれはアメリカがやったことでもあるが。 |
| 7.発電所における多層構造 |
ここ福島第二では45万m2の敷地に35の直請けと何百かの下請けがあり、膨大な数の人達が働いている。そういった多層構造の人達をいかにしてコミュニケーションを良くしていくか大変難しいことだと思う。実は事象や事故は、正式の社員ではなくて、下請けとか孫請けとかいわれるところで起こるのがほとんどである。今問題になっているサプレッションチェンバーの異物混入問題は皆さん方の誰も知らなかったと思うし、知っていたら当然止めただろう。皆さん方の手の届かないところでそういったことが行われている、行われてきたという事実を改めて目にすると、やはり事故隠しと同根の、共通した面が出てきているのではないかという気がした。しかし、ことここに至った以上、もう全部の膿を出しつくさなければならないと思う。
この多重構造の中で、社員は福島第一で840人、第二では543人という数だそうだが、例えば、放射線業務従事者を調べてみると、第一では9,543人、第二では6,821人という膨大な数である。放射線業務従事者だけでもそれだけの数の人たちが入っている。しかし、労働組合の顔が全く見えてこない。私は労働組合の人達からも別な面から話を聞いてみたい。労働組合というのは系列も含めて横断的なものを持っているので、どう考えているのかということも探ってみたいと思う。
また、情報の共有、特にトラブル情報は社員への説明よりも早く協力企業に流すようにしているということだし、社員も「安全運転宣言」や「企業倫理に関する行動基準」等たくさんのポケットブックを持っておられる。こういったもので、絶えず安全文化をしみ込ませようと努力しておられるようだ。正社員数の何倍にもあたるような協力企業の方々がいる訳であるが、上下関係ではなくイコールパートナーとしてやっていかなくてはならないということも聞いた。信頼回復というものに一番重点に置いて、地域の皆様に努力している姿を知ってもらおうと全社、全発電所あげて取り組んでいることがよく分った。 |
| 8.マニュアル事故原因 |
私は常々マニュアルというものに対し、多少の疑問を持っていた。「マニュアルというものは、守らなければならないけど万能ではない。このルールがどういう意味を持っているのか、という本質を理解しなければいけない」と発電部長さんも言われていたが、私が日頃考えていたことと全く同じである。そういった精神がきちんと活かされているということで、非常に心強く感じた。
また、「いろいろな事故や事象には直接の原因だけではなくて、背後にいろいろな要件がある。こういったものも解決して、活かしていかなければならない」とも言われていたが、これも全く同感である。
|
| 9.運転再開に向けて |
運転員の方々が、もう全部準備はできているにもかかわらず、いろんな条件で、運転再開が延び延びになり、さらに次々と目標が延びていく。大相撲の仕切り、あるいはマラソンでもどの距離でスパートをかけるかなど、スポーツ選手は非常に苦労されている。調子が狂ったら記録も出なくなる。やはり運転員の方々もそういった緊張状態を維持しながら待っているといった、外からは窺い知れないことまでも、実際に目で見たりお話を聞いて理解できた。
短時間に判断して実行していかなければならない緊張感、それから運転操作に対する「勘」といったものも、これだけ長い停止期間があると、それを取り戻すのはたいへんなことではないかと思う。そういった勘を、いつでも再開に備えられるような、研ぎ澄ました状態に持っていなければならないのは、本当に大変なことだと思うわけである。
それから、問題になった事故、事象は二度と繰り返さないと思う。もし起こるとすれば、今まで考えの及ばなかった部分から起こるのではないか。私はよく、「神々は細部に宿る」ということわざを引用するが、神様というのは人間が気付かないような、あるいは軽んじているような部分に宿っていて時々警告を与える、といった気持ちを込めたものであるが。今後は、そういった部分にも十分目を光らせていただきたいと思うわけである。 |
| 10.マスコミの問題 |
マスコミにも特有の傾向がある。読売新聞の北村行孝さんが、安全文化に関する点でマスコミの問題点を分析しているので、それを中心にお話ししてみたい。
まず、別に原子力に限らないが、とにかく何か事件が起こると、集中豪雨的な報道をする。連日トップ記事とか、お涙頂戴のようなものもある。これが一般市民に必要以上の不安感を与え、風評被害を助長する。さらに原子力の現場の方に非常に強いプレッシャーになり、跳ね返ってくる。
第二に新聞にも競争があるし、新聞の性格もあり、センセーショナルな報道に走りがちな新聞、あるいはメディアもある。従ってセンセーショナルな報道にならないように気を付けなければいけない。言い換えると、事故や事象を絶対に事件にしてはいけない。事件ということになると、扱いは社会面記事になるし、派手な見出しのお涙頂戴的な記事にもなって、その事故や事象以上に大きな影響力を与えたり波紋を広げることになる。
第三に、絶対安全というものを求めるような報道も散見される。これは、かつて皆さん方の先輩が「原子力は絶対安全だ」と言ってきたことにも因るわけである。もう10年ほど前、東京電力副社長で、今は参議院議員の加納時男さんが、テレビ朝日の朝まで生テレビに出た時、原子力には潜在的危険性があるという発言をするだけで、技術陣の大変な抵抗があったという話を耳にした。
原子力に絶対安全を求めるという思いが、一般市民の間に歪んだリスク感を醸成することになった面もあった。さらには、重要度に応じて合理的な安全対策を施そうとすることを妨げ、結果として、世間に迎合的な対策にならざるを得なかったのではなかろうか。
第四に、ジャーナリズムは一過性というか、わーっと騒いでおきながらフォローがないとよく言われる。フォローがあっても、その記事は小さくなってしまう。そのため、最初の記事が間違いや不完全であった場合、誤りがそのまま残ってしまうのも非常に気になる。
第五に、物事を単純化しがちである。本当は灰色であっても白か黒か割り切る。皆さん方の言い分にも何分かの理があるが、それは切り捨ててしまって、強い方というか迎合的な方にだけなびく。要するに判りやすくインパクトがあるニュースというものを、どうしても大きく取り上げるということになる。複雑な背景があるにもかかわらず強引に単純化してしまうということがある。
第六に「悪」と決まったら、非常に勧善懲悪的な、懲罰的な報道をする。原子力のような複雑なシステムの事故原因は単純ではないにもかかわらず、象徴的な犯人を求めたがる。また再発防止のための原因調査と責任追及を混同する。これは今度、東電の方々も身にしみて感じられたのではないかと思うが、こうした問題が複雑に絡み合って、皆さん方の中にマスコミ不信がかなり大きく膨らんでいるのではないかと思う。
もちろんマスコミは万能ではないし、第三者の批判も受けなければいけない。最近はマスコミ同士も悪い点を互いに取り上げており、自分だけは良いというような態度をとり得ないし、反論も許さざるを得ない時期に来ている。このことはマスコミ自体も気付いており、反論の場も用意している。
今度の一連の事件で一番問題だった行為は、ご存じのとおり気密試験の偽装工作だったと思う。朝日新聞が科学欄で非常に詳細にこの問題を取り上げていた。しかし社会面や一面で取り上げられた問題を、例えば科学欄で後でいくら詳細に書いても、ほとんど読んでもらえない。そのほか、時間的な制約というものも確かにあるわけである。 |
| 11.ヒューマンエラー |
ヒューマンエラーと言っても、それで片付けられてしまうのはとても解せない。例えばTMI、これもヒューマンエラー。どうしてこのヒューマンエラーが起こったのか。例えばご存じのとおりTMIの発電炉はGEでもWHでもない第三のメーカーの製品で、当時、「非常に性能はいい、ただ運転が難しい、スポーツカーみたいなものだ」とも言われていた。アメリカでは潜水艦の運転員が退役して原子力発電所にずいぶん就職していたが、あの運転者もそうだったそうだ。別に潜水艦の運転員あがりだから悪いとは言わないが、潜水艦のコントロールルームと発電所の大きなコントロールルームとはだいぶ違うと思う。あるいは慢心とか慣れといったものが、確証はないがあのような事故を生んだのではないかという気もする。
確証があるのはチェルノブイリである。チェルノブイリはタービンがトリップした場合に、その惰性でどれだけポンプ等の機器へ電気を補給できるかというテストだったと言われている。そんなテストをあんなときにどうしてやる必要があったのか?がまず疑問である。本来ならば完成までの試験運転のときにやっておかなければならないはずである。ところが、完成を早くすると報償金がもらえるというので、それで試験を抜きにして完成させた。そうして後でこっそりとやったというのが真相だという。このへんはほとんど知られていないが、十把一絡げでヒューマンエラーと片付ける前に、納得できない何かが裏にあるのじゃないか、そういったことをぜひ調べて頂きたいと思う。
例えば、JCO事故の時の屋内退避、あれは完全に不必要だったというのがジャーナリストの常識になっている。というのは原子力安全委員が完全に初動を誤ったわけである。そして夜になってあんなことになって大慌てになった。当時の記録を見ると「これは重大なものには発展しない」と言っている、安全委員の中の一番の専門家が見誤りを犯している。
そしてもんじゅの問題。熱電対のさやが折れたわけだが、さやはどうしてあんなことになる設計だったのか?実はさやの細い部分と太い部分の間にアールが無い。しかもそれがナトリウムの流れの中に入っていて、異常振動起こして折れたわけであるが、そんな温度計をどうして設計したか?実はI社が設計したのだが、I社は東京の町工場へ下請けに出した。町工場の工員さんが「これでは折れる。こんな設計でいいのか?」と電話したら担当者は「アメリカ機械学会の規格がこうなっているのだ」という答えたというのだが、実はアメリカ機械学会の古い規格だった。これはもう有名な事実だが、すでに動燃に引き渡した後なので、T社なりI社の責任は問えなかった。私が調べてみると、両社はかなりの額の"お詫び金"を動燃に払っている。こういったものは全く新聞には出ないので、私は反対派のインターネットへの書き込みで発見した。そういった貴重な情報が、反対派の方から出てくるというのでは、本当の意味での情報公開とはいえないのではないか。 |
| 12.おわりに |
アメリカの原子力規制委員長を務め、そして米国に維持規格を導入した功績者であるシャーリー・アン・ジャクソン博士(女性)が10月に来日した。マサチューセッツ工科大学(MIT)で素粒子論を専攻し、卒業して政府機関に入った人であるが、彼女にどうして維持規格を導入する気になったのかを聞いてみた。そうしたら有名な「TIME」という雑誌の表紙を見せてくれた。それには一人の技師が映っていて"Whistle-blower"(内部告発者)とあった。
実は彼は原子力発電所が隠していた欠陥を内部告発した張本人で、雑誌の論調は英雄扱いであった。そのあと、一般世論も新聞も全部、原子力規制委員会に非難を集中したが、電力会社は全く批判されなかったそうだ。原子力規制委員会は監視する立場にありながら、どうして見逃したのか、というのである。3000人ものスタッフ抱えたアメリカ原子力規制委員会は、それだけの権限もあれば責任もある、何かあれば全部責任を問われる。スタッフはみんな落ち込んでしまった。そうしたときに、誰かが壁にスローガンを掲げた。
私は今回のピアレビューで、この発電所でもいろいろなスローガンを見た。たくさんありすぎてどれもピンと来なかったが、アメリカ原子力規制委員会のその時のスローガンはこうだった。
"The bend of the road is not the end of the road, unless you fail to make the turn. "
日本語に訳すと、「道路の曲がり角は、道路の行き詰まりではない。但し、曲がり損なった場合には、それは行き詰まりになってしまう」ということになる。
今、皆さんはまさに大変な曲がり角に差し掛かっている。しかしながら、決して曲がり損なわないように留意して、正しい歩みを続けていけば、必ずや新しい道が開けてくるのではないか、と私は思う。
|
(別紙) |
|
尾崎 正直 氏 プロフィール
| ○経歴 |
| 1924年 |
愛知県豊橋市生まれ |
| 1947年 |
名古屋大学工学部機械工学科卒業 |
| 1949年 |
同大学院特別研究生(前期修了) |
| |
朝日新聞社に入社
| |
ニューヨーク特派員、科学部長、北海道支社次長、
朝日ジャーナル編集長、東京本社編集委員(科学技術担当)などを経て |
|
| 1983年 |
定年退職 |
| その後、大東文化大学、静岡理工科大学、静岡産業大学の非常勤講師を勤めた |
| 1995年、1997年、2000年、各1ヶ月 北京外国語大学国際交流学部客員教授 |
|
| ○主要著書 |
・ |
「科学技術の最前線」(全14巻 ダイヤモンド社) |
・ |
「21世紀への助走」(朝日新聞社) |
| |
など多数 |
以上
|
|
 |
|
  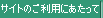 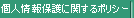 |
| Copyright © 2005 Japan Nuclear Technology Institute, All Rights Reserved. |
|
|